WEBプロダクトで
消費者とビジネスの
距離をゼロにする児玉 光史

拡大する市場のなかで
WEBディレクターが果たす役割とは
スマホ一つで何でも購入できる時代、消費者の行動は大きく変化しています。
消費者との接点が急速に変わる今、私たちはどのように対応すべきでしょう?
わかりやすい例としてEC市場の数字を取り上げてみます。
国内のEC市場は2014年から2023年までに約1.94倍に拡大し、世界的には2029年までさらに63%の増加が予測され、話題になりました。
これまでもこれからも、“オフライン(リアルな店舗)での消費”から“オンラインでの消費行動”にデジタルシフトが進み、WEBを起点としたビジネスチャンスは、これまでにない規模で広がっています。
消費者との接点が劇的に変化する中、“WEBプロダクトで消費者とビジネスの距離をゼロにする” ── これは私たちの挑戦です。
そんな弊社のWEBディレクターとしての役割は、単なる制作の企画や進行管理に留まらず、消費者とのコミュニケーションがどのようであるべきかを問い直す。そして、マーケティング、テクノロジー、デザインなど多方面の専門知識を融合させることで、デジタル上の体験価値を引き出し、消費者には良い体験を、ビジネスには売上を生み出すことにあります。
最新のトレンドやテクノロジーを取り入れ、消費者と企業の境界をなくすためのWEBコミュニケーションを模索し続けています。

アプリ開発で得た経験の先に見えた
WEBコミュニケーションへのシフトチェンジ
私は、この業界でのキャリアをiPhoneアプリエンジニアとしてスタートさせました。しかし、経験を深めるなかで「なぜその技術を選ぶのか」「お客さまの本当のニーズは何か」という素朴な疑問が生まれました。
2014年頃、iPhoneやiPadが日本に上陸して間もなく、ネイティブアプリが大いに持て囃される時代背景がありました。しかし、企業の担当者はネイティブアプリの本当の価値や機能を十分に理解していないことが多く、求められる機能やユーザー体験もWEBサイトで実現可能なものばかりでした。
果たして、利用者にApp Storeからのインストールを促したり、各プラットフォームの開発費用を捻出したりすることが必要条件なのか、疑問を感じることも少なくありませんでした。
もちろん、インストール型アプリにしかできないことや、ビジネスとしての強みは存在します。しかし、普段のビジネスコミュニケーションやユーザー体験は、アクセスのハードルが低いWEBサイトでも十分に提供できるものが多いことも事実です。
そこで私たちは、それまで培ってきたアプリ開発会社としてのキャリアを捨て、誰もが手軽にアクセスでき、ブラウザ一つでユーザー体験を提供できるWEBサイト・WEBシステムの世界へ事業の舵を切りました。私たちがただの開発会社からWEBを通じたコミュニケーション創造を図る会社へと方向性を定めた瞬間でした。

対話とユーザー体験の仮説検証を重視した
プロジェクトの流れ
それでは、弊社がどのようにプロジェクトを推進しているかをご紹介します。
プロジェクト始動段階では、企業の担当者様との十分な対話を通じ、事業目標、ターゲットとなる消費者のニーズ、競合他社の取り組みなどを詳細に把握します。
得られた情報をもとに、社内でブレインストーミングを実施し、仮説に基づいた戦略・戦術を策定します。
私たちは、定量的なデータはもとより、ユーザーインタビューで得られたお客さまの声や、競合他社・類似業界での成功事例といった定性的情報を最も重要視しています。
まずは在るべきコミュニケーションの全体像を提示し、実現可能かつ効果的なプランとして優先順位を付けつつ、半年から年単位での施策プランを定めていきます。
全体の工程やマイルストーンを明確にしながらも、最も優先順位の高いことは“消費者のフィードバックを得る”ことだと考えています。
たとえサービスインが1年後だったとしても、初期にプロトタイプによるユーザーインタビューや、集客を検証するためのLPを整備することで、ユーザー体験の検証に重きを置いています。
プロジェクトに関わる関係者が不安を感じる「デザインもシステムも作り込んでからアテが外れた」とならないようなプランニングが強みだと自負しています。

成功と課題の両面から学び、
次につなげるプロジェクト運営
私が関わったプロジェクトの中でも、某大手企業のサイトリニューアルは特に印象深い事例です。
初期段階で、競合他社だけでなく、購買行動が近い他業界のベンチマークも抽出し、綿密なユーザー体験をリサーチしました。
その結果、消費者の購買行動に合わせた適切なコンテンツとUIを提供することで、リリース後にはPV数やコンバージョン率が大幅に向上しました。
また、リリース後も継続的にユーザーインタビューやABテストを実施し、より適切な情報やデザインを検証し続けることで、まさに「WEBプロダクトで消費者とビジネスの距離をゼロにする」ための取り組みを推進しています。
一方で、どのプロジェクトでも、学ぶべき点や改善すべき点は必ずあります。
社内ではプロジェクト終了後に「KPTA(Keep:続けること、Problem:課題となったこと、Try:試したいこと、Action:行動すること)」MTGを実施し、経験から学ぶ機会を設けています。
例えば、Problemで上がった事項から、プロジェクト開始前の意見交換の場を増やし、お客さまの期待を損なわないための情報共有体制を強化するなど。どんな経験も決して無駄ではなく、次への糧として、自身とチームの成長に大きく寄与していると実感しています。

新しい体験のヒントは身近にある、
発想力を鍛える方法
急速に進化するデジタルテクノロジーの中で、職業柄、業界動向には敏感で、最新ツールやプラットフォームの活用はとても興味があります。
私自身が頻繁に利用するECサイトや各種アプリ、店舗とのオンラインコミュニケーションなど、自らが実験台となって良いユーザー体験と悪いユーザー体験の両方を経験することを意識しています。
優れた提案を行うためには、良いものとそうでないものを見極める目を養う必要があると考えています。
また、SNSなどを通じてWEBやマーケティングに関する最新の考え方やテクノロジーが流れてくる中で、それらを蓄積し、社内勉強会などで共有することで、業務や提案内容をチーム全体でアップデートしていくことも重要です。
特に、消費者の行動パターンを把握する手法は、デスクトップサーチからユーザーインタビューまで多岐にわたります。
皆さんと話している中で、ふとした瞬間の「こうしたほうが良い」「これを取り入れてみたら」というアイデアが、コンテンツや施策が大きくコンバージョン向上につながるケースもあります。
新たな企画を考える際、従来に無いものを作ろうと躍起になる方もいますが、新しい施策やユーザー体験のヒントは実はあらゆる場所に散らばっています。
時には、テクノロジーとクリエイティビティの双方の視点から「こんな体験が実現できたら面白いのではないか」と、メンバー同士が補完し合い、刺激し合うことで、価値ある取り組みが生まれると信じています。
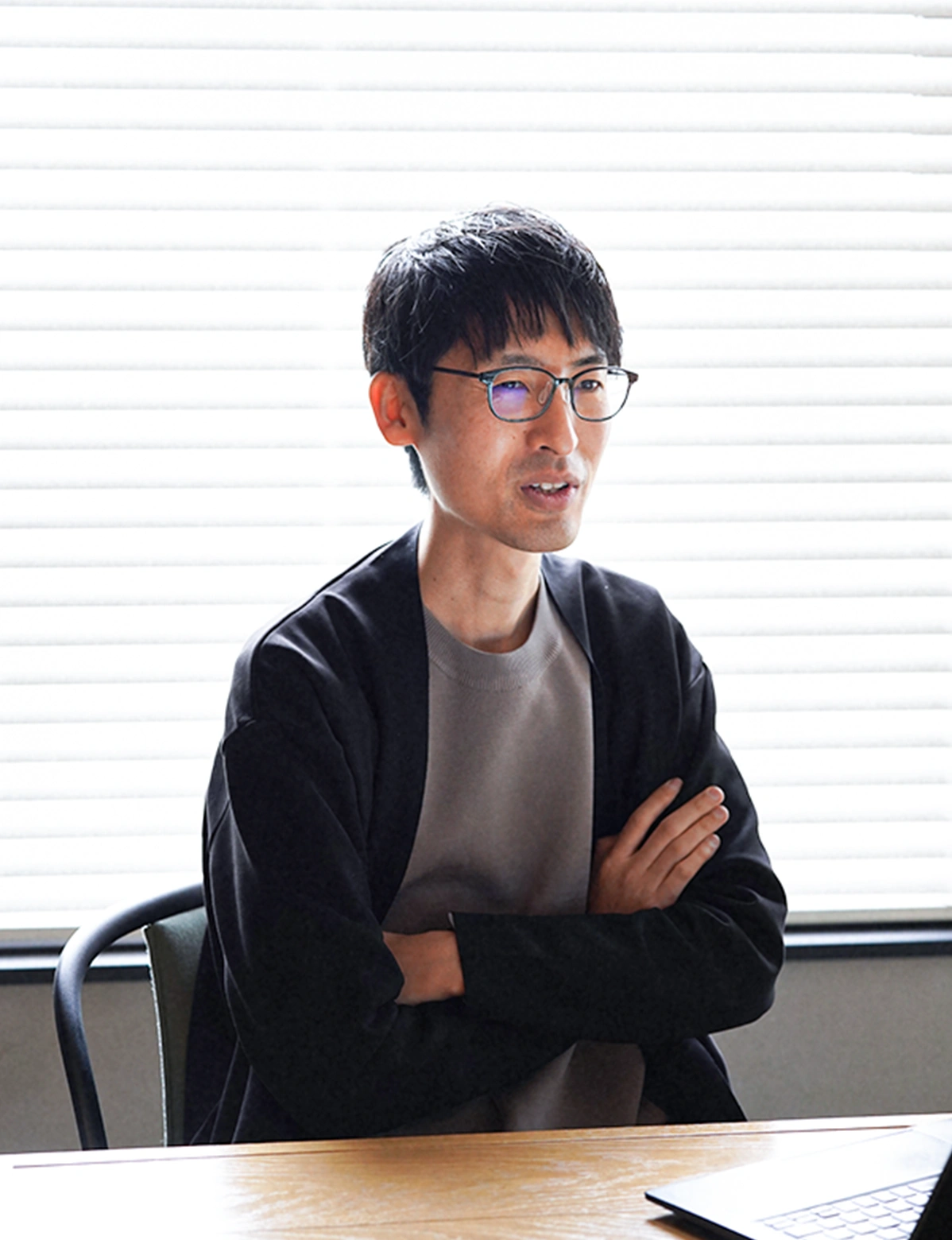
思考は実行のためにある、試し、学び、
成長し続ける
消費者がどのようなニーズを持ち、どの接点でどんな興味を抱き、物やサービスを利用するかという基本的なテーマは時代が変わっても普遍です。
常にWEBを見て触る人の視点で物事を考え、仮説と検証を繰り返すことが重要です。
しかし、これからのWEBマーケティングは、AIを中心としたこれまでにないテクノロジー革新により、取得できる情報量や分析手法が大きく変わろうとしています。
こうした変化に柔軟に対応するためには、幅広い知識と挑戦するマインドセットが不可欠です。
私はこれまでの経験から、実行して、失敗も成功も含めた結果と経験が、ビジネスと消費者を動かし続けるための原動力であると痛感しています。
これからディレクターとして仲間に加わる皆さんには、ぜひ一緒にチャレンジして新しい経験を積み上げていっていただけることを期待しています。
未来のWEBマーケティングの最前線を、共に切り拓いていけることを心から期待しています。


2004年4月〜2008年3月 南山大学 総合政策学部
2007年4月〜2008年3月 株式会社フランチャイズアドバンテージ
2008年4月〜2011年3月 株式会社CBRE
2011年4月〜2012年8月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
2012年9月〜現在 株式会社Lifebook